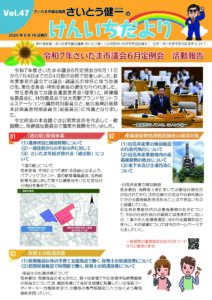保健福祉委員会の議案外質問 令和7年6月23日
質問要旨
1,要支援世帯の支援について
(1) 早期発見の通報等ガイドラインについて
(2) 要支援世帯の支援拒否について
(3) 支援前の事前準備について(任意後見制度の推進)
2,介護士の人材確保について
(1) 介護士の処遇改善について
(2) 介護士のイメージアップへの取り組み
3,シルバーポイント登録団体の対象拡大について
(1) 学校防犯ボランティア団体の登録

1,要支援世帯の支援について
(1) 早期発見の通報等ガイドラインについて
(2) 要支援世帯の支援拒否について
(3) 支援前の事前準備について(任意後見制度の推進)
○斉藤健一委員 公明党さいたま市議会議員団の斉藤健一です。 それでは、通告に従いまして質問させていただきます。
1、要支援世帯の支援について、こちらさいたま市が発行している早期発見の通報等ガイドラインについて質問いたします。 初めに、ガイドライン作成の経緯について、さいたま市が要支援世帯の早期発見に関する通報等ガイドラインを作成した背景や経緯について質問いたします。
また、ガイドライン作成に当たり、現場や関係機関から寄せられた課題や意見、御指摘等がありましたら、その内容も質問します。
2点目に、ガイドラインの活用と周知について。策定されたガイドラインがどのような場面や対象者に活用されているのか。主な活用事例や対象となる世帯像について質問いたします。また、市民や関係者に対して、ガイドラインの内容や重要性について、どのような方法や工夫で周知啓発を行っているのか、広報や取組について質問いたします。 さらに、ガイドラインの周知後、実際にどのような効果や変化が表れているのか、通報件数や支援につながった事例等、実績や課題についても質問いたします。
3点目に、通報者保護として安心して通報できる環境整備について、通報を行った方がその行動によって特定されたり、報復や不利益を受けることがないよう、市としてどのような対策を講じているのか質問いたします。また、通報者が安心して通報できるよう、匿名性の確保や相談体制の整備等、具体的な取組や対策についても質問します。 さらに、通報者が心理的な負担や葛藤を感じることなく通報できるよう、市としてどのようなメッセージ発信やサポートを行っているのか、以上、質問をいたします。 よろしくお願いします。
○福祉局副理事(地域共生担当) 斉藤健一委員御質問の(1)要支援世帯の早期発見のための通報等ガイドラインについてお答えいたします。
このガイドラインの作成の経緯につきまして、きっかけといたしましては、平成24年にさいたま市において、一家3人の方が、どこにも相談することもなく気づかれずに自宅で亡くなられ、遺体で発見されるという痛ましい事件が起きましたことがきっかけでございます。 このような孤立死の発生を防ぐために、支援が必要な状態であっても、自らSOSのサインを出さない、あるいは出せない要支援世帯を早期に発見することが重要であると考え、発見・通報のためのガイドラインを平成24年に作成いたしました。 このガイドラインには、誰もが異変に気づき通報しやすいよう、通報の基準例を明確に示しております。この基準例につきましては、民間事業者や福祉関係者、消防の職員などから聞き取りを行いまして、「異変と思った」「心配になった」などといった体験に基づき策定させていただいたものでございます。
続きまして、ガイドラインの活用と周知等についてでございます。 本ガイドラインは、誰もが通報に気づきやすいよう、通報すべき異変と思われる基準例、民間事業者が業務の中で異変を発見した場合の通報基準、通報先、通報を受けた行政機関のその後の流れを示しております。活用事例といたしましては、お独り暮らしの高齢者宅へお食事を届けた際に、いつもお会いできる方に会えないといったことから通報されたという事例がございました。また、近隣の方から、最近姿を見かけないといった通報もございます。対象となる世帯像としては、お独り暮らしの方が多くなっていると考えております。
周知啓発につきましては、市のホームページに掲載をし、周知を図っているほか、区役所福祉課等でチラシの配布を行っております。また、小型の小冊子を作成いたしまして、協定事業者が業務を行う際に、携帯し活用いただけるよう配布をしております。 通報件数につきましては、昨年度、令和6年度の通報件数は17件でございました。平成24年度からの累計では204件の通報となっております。その中で無事が確認できた、転居しているのではないかと思われる案件が7割を占めております。この無事が確認できた事例の中には、民生委員などによる見守り活動につながった、生活保護制度の被保護者となったなど、行政等の支援につながった事例がございます。
課題といたしましては、この事業は孤立死未然防止対策を強化するために作成され行ってまいりましたが、対象となる方の多くがお1人の世帯であることから、今後は孤立孤独対策として、より広い視点での取組が必要であると考えております。
また、通報者保護としての対策でございますが、本事業はあくまでも人道的な見地から異変を感じた場合に通報をお願いしているものであります。通報を義務づけるものではありません。しかし、通報される方が不安を感じることがないよう、安心して通報していただけるよう、ガイドラインのQ&Aにおいても、個人情報について取り上げているところです。また、民間事業者と協定を結ぶ際にも、通報者の情報は個人情報として保護されるよう匿名とすることをお伝えし、共有しているところでございます。
○斉藤健一委員 次の質問に移ります。 (2)要支援世帯の支援拒否について質問いたします。 要支援世帯から行政による支援を拒否された場合、プライバシーや本人の意思の尊重と命や生活の安全確保をどのように両立していくべきかが重要な課題であると考えます。 そこで、以下、質問させていただきます。
初めに、要支援世帯から支援を拒否された場合、本市の基本的対応方針を伺います。そして、プライバシーと本人意思の尊重を前提としつつも、命や生活の安全を確保するための具体的な対応事例や実際の手続の流れについても質問いたします。
また、繰り返し支援を拒否されている世帯に対して、市が実施している粘り強い支援策について伺います。具体的には、見守りや再度のアプローチ、関係機関との情報連携、さらには地域住民による見守り活動の活用など、継続的な支援のための取組について、市はどのように関わっているのか質問いたします。
さらに、支援拒否が長期化した場合や緊急性が高まった際の対応について伺います。権利擁護の観点からの対応など、市として最終的な安全確保及び権利保護の手段について、どのように考えているのか、市の見解を伺います。
○福祉局副理事(地域共生担当) 斉藤健一委員御質問の(2)要支援世帯の支援拒否についてお答えいたします。基本的対応と具体的な対応事例や実際の手続の流れでございますが、支援を拒否するケースに対する本市の対応でございます。まずは、相談を受けた区役所や相談支援機関において、対象者の状況を把握した上で、関係性を構築しながら、本人の意思を尊重しつつ、必要な支援につなげるための働きかけを行っているものと認識しております。また、対象者が複合的な課題を抱える場合は、福祉まるごと相談窓口において包括的に相談を受け止め、複数の関係機関による連携した支援を実施しているところでございます。
具体的な事例といたしましては、セルフネグレクトで拒否するケースが挙げられます。生活環境が悪化しており、医療への受診や介護、障害サービスの導入をするようなセルフネグレクトの方に対しましては、御家族などキーパーソンとなる方や関係機関と協力をして本人を説得するように取り組んでおります。
粘り強い支援策につきまして、関係機関との情報連携、見守り活動の活用などにつきましては、特にセルフネグレクトのケースなど、繰り返し支援拒否をする世帯に対しましては、まずは信頼関係を構築できるように定期的に訪問するなど、粘り強い対応に努めております。
また、今年度から配置しておりますコミュニティソーシャルワーカーにつきましては、個々のケースの状態にはよりますが、周囲から見て支援が必要にもかかわらず支援を拒否している方は、支援対象となる可能性が十分にございます。 具体的な課題解決を強みとする行政に対しまして、コミュニティソーシャルワーカーの特徴は、支援を拒絶している場合であっても、継続的なアウトリーチによる伴走型支援により、寄り添いながら長い時間をかけて丁寧に関係を築いていく点にあります。つながること、孤立させないこと、こちらを目的とする伴走型支援を拒否するようなケースには有効であると考えております。コミュニティソーシャルワーカーの対応事例では、支援拒否の傾向のある方に対し、民生委員や関係機関と共に、緩やかな見守り活動の体制を構築した事例もございます。今後もこうした地域の連携体制を積極的に活用してまいります。
また、支援拒否が長期化した場合や緊急性が高まった場合につきまして、本人の生命や身体に深刻な影響が出る前に、何度も訪問いたしまして、介護保険サービスや障害福祉サービス等の導入を粘り強く働きかけてまいります。 それでも緊急性の高い状況に陥った場合には、必要に応じて警察や消防と連携し、入院させることを検討するなど、本人の安全確保に努めてまいります。
○斉藤健一委員 今年度からCSWの配置も決まりましたので、アウトリーチにしっかり力を入れていただきたいと思います。 (3)支援前の事前準備について質問いたします。 近年、家庭内での孤立が進む高齢者や生活上の困難を抱える世帯が、既存の支援体制の谷間に陥り、セルフネグレクトへと移行する事例が報告されています。こうした現状を踏まえ、要支援世帯認定前の段階での早期アプローチが重要と考えます。そのため、セルフネグレクトに至る前の予備的段階から、支援の目が行き届く仕組みづくりが不可欠です。
初めに、シニアサポートセンター、社会福祉協議会、医療機関、民間団体等、多様な主体が連携して事前支援を取り組む体制づくりの現状について伺います。 また、データや情報共有とリスク予測の活用について、健診結果や福祉サービス利用状況、地域からの生活実態把握など多様なデータを統合分析し、セルフネグレクト移行リスクの高い世帯を早期に抽出するための情報共有やICT活用で事前準備の強化を図ることについて、市の見解を伺います。
○福祉局副理事(地域共生担当) 斉藤健一委員御質問の(3)要支援前の事前準備についてお答えいたします。 シニアサポートセンター、社会福祉協議会、利用民間団体など多様な主体が連携して、事前支援に取り組む体制づくりについてお答えさせていただきます。
福祉まるごと相談窓口では、様々な課題を抱えた方などの相談を包括的に受け止め、個々の生活課題に応じて高齢、障害等の支援機関につないだり、ほかの支援機関、民間団体等と連携して必要な支援のコーディネートを行っており、地域での生活を支える体制づくりを進めております。 また、今年度から4区に先行してコミュニティソーシャルワーカーを配置いたしました。これにより、高齢、障害等の分野にとらわれない、関わり続ける伴走型支援を強化していくところでございます。 今後につきましても、引き続き庁内関係機関はもとより、庁外の関係機関、民間団体等と顔の見える関係の下、有機的な連携が図れるような体制づくりを実施してまいります。 次に、データ、情報共有とリスク予測の活用につきましては、要介護認定のデータと障害福祉のサービスの利用状況を踏まえまして、訪問調査を実施しているところでございます。このような調査の結果を踏まえまして、必要な支援につなげてまいりたいと考えております。

2,介護士の人材確保について
(1) 介護士の処遇改善について
(2) 介護士のイメージアップへの取り組み
○斉藤健一委員 しっかり支援前の事前準備ということも大事な支援かなと思いますので、引き続き、アウトリーチ支援、そして伴走型支援をしっかりお願いしたいと思います。 次の2番の質問に移ります。 介護士の人材確保について、(1)介護士の処遇改善について質問します。 本市においても、高齢化が進展する中、介護サービスの需要が年々増加している一方で、介護士の人材不足が深刻化しております。離職率が高く、担い手の確保が大きな課題となっており、現場では慢性的な人手不足が、サービス提供の質の低下や職員一人一人の負担増加につながっています。特に、若年層や中途採用の定着が進まない現状も指摘されております。 初めに、本市の介護士の人材不足について、入所施設、通所施設、訪問介護事業所別での現状認識、市はどのように捉えているのか伺います。 また、人材確保のためには、介護士の処遇改善が必要と考えます。本市が取り組んでいる処遇改善の施策で成果があるものと、今後、介護の現場で人手不足解消として力を入れてきた施策について、市の考え方や方針について質問いたします。
○長寿応援部長 斉藤健一委員の御質問の2、介護士の人材確保について、(1)介護士の処遇改善についてお答えいたします。 御質問の施設区分やサービスごとの介護職員の人材不足状況については、申し訳ございません、具体には把握していないのですが、いずれの施設、サービスでも、さいたま市のみならず全国的に人材不足が認められる状況にあると認識しております。 委員御指摘のとおり、介護職員の人材確保は大きな課題であり、介護職員の処遇改善につながるよう、本市では一昨年度に九都県市を代表して、また昨年度は本市単独で、国に対し要望書を提出し、今年度も継続的な要望として国に対応を求める予定となっております。
また、本市では、昨年度から介護事業所に社会保険労務士等の専門家を派遣する介護職員等処遇改善加算取得促進事業により、介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備や介護職員の賃金改善に向けた支援に取り組んでおり、平成6年度の実績といたしましては、市内3事業所に対し専門家を派遣し、個別相談を実施しました。その結果、3事業所とも、より上位の加算区分を取得することができましたので、これは成果があったものと存じます。
さらに、今年度からは、経験の浅いヘルパーへの同行支援など、訪問介護事業所向けの支援を本市独自の取組として新たに始めたところです。 今後におきましても、これらの施策、あるいは新たな施策も検討しながら、介護職員の処遇改善につながる取組を図ってまいりたいと存じます。
○斉藤健一委員 介護人材の人手不足は認識していると。そのために施策を実行している。それで、また新たな処遇改善も検討していきたいという答弁がありました。 2024年の総務省のデータによると、さいたま市の全産業における平均年収は約447万円、そのうち、これはさいたま市というよりは埼玉県全体になってしまうんですけれども、介護士の平均年収は約351万円で、全産業よりも年収が約100万円やっぱり低くなっております。 さいたま市は同じような現状で、保育士に対しては、市独自の賃金上乗せ補助を行っております。この介護士に対しても、市独自の賃金上乗せ補助を行っていくということに関しては、今どのようにお考えでしょうか。見解を伺います。
○長寿応援部長 御質問の前に申し訳ございません、初めに発言訂正をさせていただければと存じます。 先ほど処遇改善加算取得促進事業の実績、令和6年度の実績で3事業所と申し上げるべきところを、平成6年度と申し上げたようでございます。大変失礼しました。令和でございます。
そして、御質問の賃金上乗せの関係についてお答えいたします。 委員御指摘のとおり、介護職員の賃金については、残念ながらほかの産業に比べて明らかに低い金額となっており、また現場の声としても本市に届いており、早期に解決すべき課題であると存じます。 基本的な対応としては、国の介護報酬の引上げに等によりなされるべきものと考えますが、本市といたしましても、財源の関係もございますので容易ではないのですが、賃金の上乗せ、あるいは事業所への補助、支援金への対応について検討してまいりたいと存じます。
○斉藤健一委員 前向きな検討を期待したいと思います。 (2)介護士の人材確保に向けたイメージアップの取組について質問いたします。 介護士を特に若い方が職業の就職先に選んでいただくためには、職業選択肢の中に入ることが大事だと考えます。そのためには賃金を高くすることだけではなく、就職する前に介護士のイメージや認知度を高める必要があります。さいたま市の介護士イメージアップに向けた取組として、令和5年度から介護現場で働く人材を市のホームページで紹介する魅力発信事業などを行っていますが、どれも介護士に興味を持った方が、自ら情報を取りに行かないとイメージ情報が得られません。
4月に山形県のやまがたKAiGO PRiDEキャンペーンの取組内容について視察してきました。この事業では、介護、教育、行政などの各団体が連携協力し、各種イベントやSNS、マスメディアを通して情報発信をすることにより、介護職のイメージアップを図ることを定めて取り組んでおります。具体的には、協力事業者の一般社団法人KAiGO PRiDEのサポートによる動画作成、出前講座、そして就職前の学生によるKAiGO PRiDE部の設立、やまがたKAiGOフォーラムの開催や、子供が楽しく遊べるお仕事体験ができるキッズタウンやまがたに介護のお仕事の出展及び広報事業を行っています。事業のメインターゲットが小学生を含む若年層ということもあり、介護職員数の増加という直接的な経過が出るまでは時間がかかりますが、将来必要となる介護士の人材確保に向けて、若い方の職業選択肢の中に介護職が自然に入ることで、将来確実な成果に結びつくように取り組んでおりました。 さいたま市も介護士不足の課題があるため、山形県が取り組んでいるKAiGO PRiDEを参考に、小学生を含む若年層をターゲットとしたイメージアップ施策を強化し、将来の人材確保を図ることについて、市の見解を伺います。
○長寿応援部長 斉藤健一委員の御質問の2、介護士の人材確保について、(2)介護士のイメージアップへの取組についてお答えをいたします。 若い世代を含め、介護士のイメージアップへの取組につきましては、本市においても重要であると考えております。 本市の介護士のイメージアップの取組としては、委員お示しのとおり、介護現場で働く職員の生の声を配信する「介護の仕事のいいトコロ」というコンテンツを市のホームページで公開し、イメージアップに取り組んでおります。このコンテンツの記事の募集に対し、令和5年度は20事業所、令和6年度は37の事業所から応募があり、それらの記事を同ホームページで公開したほか、県内外の教育機関への情報提供もしているところです。 あわせて、このコンテンツの周知として、これまでさいたま市のホームページのトップページにて、期間限定ではございましたが、バナーを掲載してコンテンツにアクセスしやすくするとともに、市の公式SNSでの周知や市民アプリへの記事掲載、メディアへの情報提供の実施など、周知は図ってきたところでございます。
今後も、委員御紹介の山形県をはじめ、他自治体等の先進的な事例を参考にさせていただきながら、よりよい情報発信を行うこと等によって、若い世代も含めてイメージアップを図り、介護人材の確保につながるよう努力してまいりたいと存じます。

3,シルバーポイント登録団体の対象拡大について
(1) 学校防犯ボランティア団体の登録
○斉藤健一委員 間違いなく介護士は人手不足の将来予測があり、さいたま市もそれに入りますので、今からしっかり準備を、しっかりお願いをしていただきたいと申し上げて、最後の質問に移ります。
3番、シルバーポイント登録団体の対象拡大について、(1)学校防犯ボランティア団体の登録について質問いたします。 学校安全ネットワークの防犯ボランティアは、保護者や地域住民、関係団体等に登下校時における見守り活動を防犯ボランティアとして行っていただいております。見守り活動の際には防犯ベストの着用をお願いし、見える化を図ることで、より防犯の効果を高めております。子どもたちの登下校の見守りとして欠かせない防犯ボランティアに登録している方たちのほとんどは、地域の70歳以上の高齢者の皆様であります。活動に必要な防犯ベストや帽子、道路横断時の旗など劣化して交換が必要になっても、各小学校の消耗品の予算が年間1万5,000円のため予算が回らず、自費で交換している方もおります。
また、本年6月からは、厚生労働省が企業に対して、職場の熱中症対策を罰則つきの義務化にしました。しかし、防犯ボランティアの方たちは、炎天下の下でも熱中症の対策も自費で対策し、見守り中に自分が倒れないようにしております。そのような中、何も恩恵もなく活動していただいていますが、新しく参加する方が少なく、年齢とともにモチベーションが下がり、辞めていく人が多いと聞きます。
そこで、貴重なボランティア活動に参加していただいている65歳以上の方に、少しでも市からの感謝の気持ちで、福祉局が行っているシルバーポイント、長寿応援ポイント事業の登録団体にしていただいて、最大5,000円の恩恵が受けられるようにしていただきたいと要望いたします。市の見解を伺います。
○長寿応援部長 斉藤健一委員の御質問の3、シルバーポイント登録団体の対象拡大について、(1)学校防犯ボランティア団体の登録についてお答えいたします。 まず、長寿応援ポイント事業の登録団体につきましては、1回の開催当たり、65歳以上の方が5名以上参加が見込まれること。あと、原則月1回以上の活動、あるいはイベントを開催する予定があること等を要件としております。 委員から御質問がありました市内の各小学校における防犯ボランティアにつきましても、これらの要件を満たす団体として登録いただければ、長寿応援ポイント事業を活用いただくことは可能です。そして、防犯ボランティアの皆様への周知等々につきましては、事業のPR方法を工夫しながら、登録団体の増加、防犯ボランティアの方々への取得促進、ボランティア登録の促進というか呼びかけについては努めてまいりたいと思います。
○斉藤健一委員 登録ができるということを確認できました。ぜひ、そのことを知らないボランティア団体がおります。学校安全ネットワークにも周知徹底をお願い申し上げて、質問を終わりにいたします。